デンマーク博覧記
―あこがれの地へ―
 毎年4月に行なわれるデンマークの国際児童演劇祭に行って来た。今年は第38回目となり、開催地は首都コペンハーゲンから列車で1時間程の、ネストヴァ市という人口77,000人のデンマークでは大きな町である。
毎年4月に行なわれるデンマークの国際児童演劇祭に行って来た。今年は第38回目となり、開催地は首都コペンハーゲンから列車で1時間程の、ネストヴァ市という人口77,000人のデンマークでは大きな町である。
4月の6日〜13日の日程で130余りの劇団による500を超すステージ数はどれもバラエティーに富んでいて、あれも観たい、これも面白そうと食指が動く。過密なスケジュールをいかに効率よく観られるか、出発前のあわただしい事務局はフェスのタイムテーブルづくりに翻弄されたようだ。
デンマークをはじめ北欧の作品、芝居づくりにはCAN青芸は少なからず影響を受けている。海外のフェスや沖縄のキジムナーフェスタに参加する作品の中でも、やはりスウェーデン、デンマークといった北欧の劇団が、人気・質の面でも群を抜いてクウォリティーが高い。15、6年前に出会ったスウェーデンの「小さな紳士」という作品は、いまだに世界のフェスからのお呼びが多く、各国の劇団上演も多くされているという。その俳優の品格、構成の妙、メッセージ性に大きく啓発された僕たちは、CAN青芸の旗揚げの時、活動の思いと創造理念の大きな拠り所とした。
そんな北欧の中でも、まだ訪れたことの無かったデンマーク。ことに毎年行われているという演劇祭は我が劇団CANならずとも日本の児童・青少年演劇界のあこがれの聖地(メッカ)なのである。
 私達3人は4月9〜15日の1週間、5日滞在の内3日の観劇日で、16本の芝居を観まくった。まさに間隙を縫うようにというか、エコノミックアニマルよろしくサンドウィッチを片手にバスを乗り継ぎ、乗り遅れしながらトンビのごとく会場を飛び回った。綿密なスケジュールを組んであるつもりも、「これは観ておいた方がいいよ」という情報が入ろうもんなら、全体がトコロテン式に変更となり、1本観るのに3本つぶれるという駆け引きに3人で悩みながら、苦渋の選択を強いられる辛い立場の事務局長の、スケジュール表と必死に格闘している雄々しい姿がそこにはあった。
私達3人は4月9〜15日の1週間、5日滞在の内3日の観劇日で、16本の芝居を観まくった。まさに間隙を縫うようにというか、エコノミックアニマルよろしくサンドウィッチを片手にバスを乗り継ぎ、乗り遅れしながらトンビのごとく会場を飛び回った。綿密なスケジュールを組んであるつもりも、「これは観ておいた方がいいよ」という情報が入ろうもんなら、全体がトコロテン式に変更となり、1本観るのに3本つぶれるという駆け引きに3人で悩みながら、苦渋の選択を強いられる辛い立場の事務局長の、スケジュール表と必死に格闘している雄々しい姿がそこにはあった。
初日の1本目、イタリアからの招待作品はさすがに呼び声高く、軽やかな音楽と共に、家族の大切さ生き方の自由と対照させて、繰り返す日常のはかなさ、虚しさといったものをテンポとデフォルメされた動きで楽しく魅せる。陽気なイタリア人気質と笑劇(ファルス)の伝統が垣間見える上質のものだった。
2日目を終えてすでに11本を消化している。夜ホテルでの3人の中間感想会で出た意見では、とにかくどの作品も見応えがあり、そしてどの劇団も構成や演目に重複が無い。どの劇団もメッセージ性がはっきりしているからいきおいオリジナル作品が多く、古典や原作ものは余程劇団の強い個性が発揮出来なければ手を付けないのだろう。人形劇「ロミオとジュリエット」などはその成功例で、逆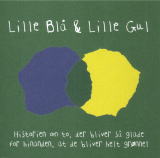 に舞台劇「青ちゃんと黄色ちゃん」などは、若い俳優のカンフーを取り入れた演出など、枝葉末節に重きを置いて主題がどこかへ行ってしまったなんていうものもあるにはあった。
に舞台劇「青ちゃんと黄色ちゃん」などは、若い俳優のカンフーを取り入れた演出など、枝葉末節に重きを置いて主題がどこかへ行ってしまったなんていうものもあるにはあった。
もう1つ。観客の年齢制限のこと。各劇団対象年齢を1.5〜4とか5〜11、6〜10、7〜11、中には6〜99などというものもあり対象年齢だけ見ていても楽しくなるのだが、これは自分達の作品を責任もって伝えたいことの現われではないか。この1歳、2歳の違いに劇団のテーマ性や表現のこだわりがあるのだろう。例えば〜99というのも、ある年代だけをすっぽりと取っても観せる事のできる作品ということだ。日本の作品の中でも時折「こどもから大人まで楽しめる」という案内を目にする作品があるが、こうしたものはデンマーク作品を凌ぐ余程優れた作品なのだろうと推察している。観れる作品と、観せたい作品とは言うまでもなく作り手の責任の所在が全く違うのである、ということでCANはデンマークに共感している。
3日目の最終日。1本目は朝10時からフェス本部から一番遠い場所にある小学校での公演。バスに乗り遅れると残りのスケジュールが変わって来る。8時30分にはホテルを飛び出した。
―圧倒された人形劇―
Boxy George(対象年齢 5〜10歳)
 ただの白い箱なのだ。
ただの白い箱なのだ。
物語りは無く、年寄りが箱と出会って戯れて、それだけの30分程の人形劇に圧倒されてしまった。
観客を迎え挨拶を終えると、黒衣の3人の人形使い達は真っ暗な小さな舞台の奥に消えていく。ブラックライトで浮き出て来たのは50cm程の白衣の老人が、黒いまな板程の小さな台の上に立ち中空の中で静に漂っている。老人が本舞台に下りるとその前に突然現われる小さな白い箱。箱たちは動き始め、老人を観察したり相談したり(と見える)。やがて追いかけっこの様になると突然箱から足が生えて人間の子どものような仕草をしながら、ダイナミックに重なったり隊列を組んだり。そして2回り程の大きな箱が幾つか現われたかと思うと、消える。独りになった老人の上から、いつしか手のひらに乗るほどの小さな白い箱が降りて来る。ゆっくり、ゆっくりと。手を差しのべるとふわっと反発するように地面に落ちて行く。いくつも、いくつも。やがてプロローグの黒い板の上に乗っている縮小された老人と、落ちている小さな無数の箱が静かに中空に漂っている。そして舞台奥に小さくなって消えて行く。
黒衣に黒手袋の人形師が操る6個の箱達が、人格を持って、遊んだり何やら考え事をしたりコケたりしている様は、凛とした透明(真っ暗)な空間と静かなBGMの中で、なんとも微笑ましい。箱達の生き生きとした動きと、日常の何気ない風景を、声高に語らない散文詩のような情感に、人生の万感をそして演劇の崇高を感じる。
終演後60〜70人の盛大なる拍手の後、演者に抱きついて泣いている中学生位の女の子。言葉少なに、でも演者から離れようとしない高学年ほどの男の子。ビデオを回しながら、不覚にも私もハラッと涙が出てしまった。皆にはどんな世界に写ったのだろう。何の世界なの?あれは誰?いや聞かないのもまた楽し・・・なのである。
帰りのバスを待ちながら、CANの3人の呟くような声は揃って「すンごいねェ・・・」。それ以外に言葉にならない。
その後の芝居は申し訳ないけど印象に残ってない。どの舞台を観ていても白い箱が頭の中に降りてきて、目の前の芝居が網膜から先まで届かない。この作品のインパクトが「白日夢」のような症状で、心地よい浮遊感が私をつつむ。帰国後1週間位、いやまだ続いているのだが、「白い箱パラノイア」とでも言うような、地に足の着かないファンタスティックなひとになってしまった。
しかし100万言を尽くしたところでこの感動を伝えられるものではないだろう。またこの思いこそ、自分達の手で新たな作品を創って観客に「なるほど!」と言わせたときに、初めてこのデンマーク博覧が価値あるものになるのではないだろうか。僕達は一観客であることと同時に崇高なる表現者の一員なのだから。
2008/4/29 清